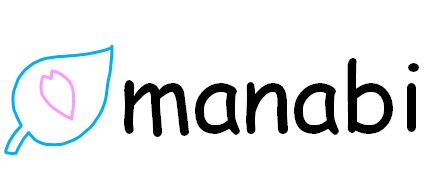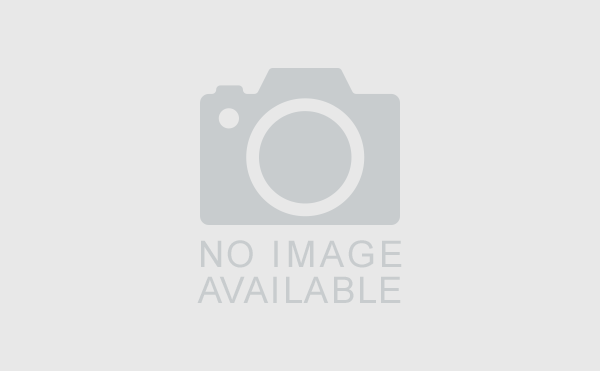【KAIZEN12】HKM用語とkaizen用語の定義を確認しよう
目次
3. HKM用語とkaizen用語の定義を確認しよう
ここで暗記する必要はありません。あとからも繰り返し出てくる言葉ですので自然に憶えてしまいます。
ふ~ん、なるほど、程度に確認をしてください。
①問題
「モンダイとは、現状と目標との『差』のこと」、として使用します。
「そして、問題とは、不具合だけではなく、不具合は無いけれどもっと良い状態・状況にしたいと言う希望や目標を含みます。」
②Kaizen(かいぜん)
「Kaizen とは、問題を解決すること」として使用します。
*「現状を目標に近づける」ことによって「目標と現状の差を無くす事」です。
*注:「KAIZEN」ではありません。「K」以外は小文字です。「KAIZEN」はトヨタ自動車で有名になりましたね。その有名効果を貰いつつ、「KAIZEN」のもつ「製造業務の改善」限定的なイメージから脱却したいという、良い所取りを狙ってみました。
③(HKM/QC/Kaizen/問題解決の)ステップ
「ステップとはそれぞれの問題解決行動を始まりから終わりまで細分化した各行動工程」として使用します。
HKMでならば覚えてもらったHKM①~⑬の行動の工程を指します
④要因(よういん)
「事態や状況を発生させている、または発生させる『原因』のこと」として、使用します。
*「数ある原因の内で、重要・主要なもの」と言うのが要因の本来の意味であると考えますが、そのようにすると「重要・主要」を決定する基準が必要となってきます。HKMでは関心が薄いところですので、要因=原因としています。
⑤実現子(じつげんし)
HKMのステップにおいては「『5.具体的実現目標』を実現するための要因として」使用しています。
*HKM全体としては「Kaizenを直接・間接に実現するための要因のこと」として使用します。従って実現子はどのステップにおいても考えられます。例えば問題をKaizenする実現子、kaizen目標を実現する実現子、実現子を実現する実現子等です。
例:「体重を5kg落とす」事の実現子は「摂取カロリーを減らす」
「消費カロリーを増やす」「運動する」「友達にダイエットを宣言する」等です。
⑥指標(しひょう)
「物事を判断したり評価したりするための目印としての数値」
と言う意味で使用します。
例:「車の走る速さ」の指標は、「時速」。 「体の重さ」の指標は「体重」。
⑦(ヒロ曼荼羅-ヒロまんだら)1巡目、2巡目、3巡目の「巡目」
同じモンダイ解決の為に、HKMを連続して実施する場合において、1回目の終了を「1巡目」、2回目の終了を「2巡目」と呼びます。
*HKMの①~⑬の全ステップを終了すると、HKMは1回終了します。
HKMを1回終了して、問題が納得のいく程度に解決できない場合には、同じ問題を対象にHKMを再度、再々度行う必要があります。このように連続してHKMを実施する場合において、一回目のHKMの終了を「1巡目」と言い、引き続いても再度のHKMを「2巡目」と呼びます。再々度は3巡目です。
「〇巡目」を「〇回目」と言っても一向に差し支えありません。
3巡したHKMをつかったKaizenは、HKMを「3回終了した」と言うことになります。つまり経験値は「3回」です。次回に行うHKMの実施は「4回目」です。
⑧分析
「事態や状況を細かく分けて、成分や構造を明らかにすること」と言う意味で、使用します。
*普通に使っている「分析」と思っていただいて問題ありません。
⑨お気楽♪
「問題解決で一番大切なことは、『問題解決活動を最後まで終わらせることだ!』と言う大きな悟りを持つこと」と言う意味で、使用します。
「必ず一応考える」こと。でも、一応考えて解らない事や、ややこしいことは「そのうちに解るようになる」ことを信じて、潔よく「ごまかして」してください。
⑩ヒロさん
「HKMの提唱者である『Kaizenおじさん』の一人称」として、使用します。
 *ヒロさんを知るキーワード
*ヒロさんを知るキーワード
1)丸い眼鏡をかけています。まん丸な眼鏡です。昔からまん丸です。
2)性格、体形も丸いです。特に眉毛はみんなが「麻呂マユ」と言います。薄くて丸いです。柴犬の眉の模様のようです。
3)世の中のある事は単独で存在することはほとんどなく、ほとんどの事象はシステムを構成している、と信じています。そう、ヒロさんの体系が丸いのは、ヒロさんばかりの責任ではないのです。
4)世の中は言葉と概念でできていると信じています。
⑪因果関係(いんがかんけい)
「それが無かったら、あれは起こらないと言う関係」として使用します。
*HKMで言う因果関係は客観的な因果関係は求めません。
普通の人が考えて「それが無かったら、普通あれは起こらない」と言う基準で考えます。
もっと言えば「考える」必要さえありません。あなたがなんとなく「それが原因だよ」と思ったことでもHKM的には因果関係ありでいいのです。
⑫「関心」(かんしん)
「達成しようとする目的や意図」と負いう意味で使用します。
*使用例:「HKMとその他の問題解決手法では関心が異なる」
「HKMの関心からQCSを修正している」
「HKMの関心からは重要性は低い」等。
*関心は大変重要です。物事の「価値」は関心によって変化します。道にできた「水たまり」は、通常は邪魔な存在ですが、砂漠で3日間水を1滴も飲まないで彷徨った人には砂漠のオワシスに見えます。
また、手を包丁で切って病院を探していると、いつもの散歩道に「こんなところに外科があった」ことに気が付くと言った具合です。
⑬コルブ経験学習(けいけんがくしゅう)
学習に関する理論。自分の行動と言う経験を通じて「知っている」を「できる」に変える為の理論です。
*「4つの工程を循環させる」と言う面を見る時には「経験学習サイクル」と言います。
*4つの工程とは、①具体的経験 ②省察的観察 ③抽象化 ④能動的実験 を言います。
「総論2」で詳しく説明をします。
⑭省察的観察(しょうさつてきかんさつ)
コルブ経験学習サイクルの4つの工程の内の1つ。具体的経験を「目と頭を使って良く観る」ことを言います。
⑮学習力(がくしゅうりょく)
コルブ経験学習サイクルの要素に必要な「観察力」「学習力」「実行力」を指すのものとして使用します。
⑯あるべき姿(すがた)
「あるべき姿とは、自分が『本来このようにあるべきだ』『成たい』『在りた』と思う状態や状況のこと」として使用します。
例:学年でトップ3に入る成績をとれる自分に成りたい。
仕事ができる自分で在りたい。
夫婦や親子はもっと仲良くするべきだ。
⑰見える化(みえるか)
「見えないのもの、見えにくいものを、目で見えるように工夫したもの」と言う意味で、使用しています。
例:ヒロ曼荼羅
ヒロ曼荼羅は形式的には、問題解決のステップ・問題解決するための思考・問題解決の全体構造を『見える化』したものです。
実質的には「お気楽♪♪」を具現化したものです。
ナムナムする対象ではありません。
つづく
By Hiro